第五回マイクロファイナンスフォーラム(1)講演:Stuart Rutherford氏(Safesave創設者) ― 2013年01月12日
昨年12月16日(日)にNPO法人 Living in Peace主催の第五回マイクロファイナンスフォーラムが開催されました。
日 時:2012年12月16日(日) 14:00〜17:30
場 所:日本財団ビル
主 催:NPO法人Living in Peace (→ 公式HP )
Ustream中継:有り アーカイブは こちら でご覧になれます
プログラム:
▼第一部(14:00~15:50)
1.Living in Peace(LIP)理事長、慎泰俊による挨拶(5分)
2.講演:Stuart Rutherford氏(Safesave創設者)(20分)
3.講演:澤田康幸氏(東京大学経済学部教授)(20分)
4.LIPプレゼン「貧困削減効果を巡る学説紹介」(15分)
5.議論「グループレンディングと貧困削減効果」(50分)
▼第二部(16:00~16:30)
1.マイクロビジネスアワード概要
2.受賞者のビジネスに関して
3.受賞者登壇 質疑応答
4.現地式典、受賞者のビジネストリップ報告
理事長の慎泰俊氏による挨拶とSafesaveというマイクロファイナンス機関創設者でもあるStuart Rutherford氏の講演をレポートします。
1.Living in Peace理事長挨拶
慎 泰俊氏
民主党から自民党への政権交代でNPOセクターにとってはどうなるか?
これまでLIPではビジネスの文脈でフォーラムを続けてきた。
しかし、マイクロファイナンスにはグループレンディングだけでなく色々なバリエーションがある。
マイクロファイナンスは本当に貧困を削減しているか?
この疑問についてどのような話があってどう考えられているのか考えてみる場にしたい。
また、今年はカンボジアからマイクロビジネスアワード受賞者も来場している。
2.マイクロファイナンス概観
スチュアート・ラザフォード氏(SafeSave創設者)
マイクロファイナンスとは?
→貧しい人々のために作られた金融サービス
始まりは1976年のバングラデシュのグラミン銀行。その特徴は
・週次のヴィレッジミーティングで銀行が貧しい人の元へ出向く
・女性に焦点をあてる
・連帯責任
・少額のローンを少額ずつの分割返済
マイクロクレジットの主張
・マイクロファイナンスは小さなビジネスをを作る
・マイクロファイナンスは貧困からの脱出を助ける
1990年代に入ると連帯責任制度は使われなくなり、個人への貸し出しへ変わっていった。
現在ではマイクロクレジット(少額貸付)から預金を含めたマイクロファイナンスへ。更にはマイクロインシュアランス(保険)や携帯電話を使ったネットバンキングまで試みられている。
・インドネシアのBRIは貧困層へ貯蓄をアピール
・マイクロ保険の誕生
・ケニアのM-PESAのような携帯電話を使った送金サービスも登場
マイクロファイナンスの資金源は当初寄付によるものだったが、1990年代後半に入ると銀行による出資
2000年代に入ると国際金融市場からの資金調達が始まった。
マイクロファイナンスはNGOを出自としていたが、上場を果たして営利企業へ転換するケースも。
2010年、南インドではマイクロファイナンスが急拡大した後、崩壊した。
急激な成長は多重債務を引き起こし、貧しい人々を債務過多に陥らせることに。
薬品の効果測定に使うRCTと呼ばれる手法でマイクロファイナンスの効果を測定したところ、貧困からの脱出にポジティブな効果はほとんどないことがわかった。
マイクロファイナンスは当初の理念に戻る必要がある。
収入が1日1〜2ドルの場合、そのほとんどが食べ物や薪などの燃料に使われてしまう。
収入が小さくて不安定ならお金のやりくりは難しい。
お金は稼いだ時に必要なのではなく、日々の生活に必要なもの。
緊急事態やお祝いごと、教育、行事などへのお金も必要。
ビジネスのための金融から貧しい人々のお金のやりくりのための金融へ。
そうした理念で SafeSave は1996年にバングラデシュのダッカで誕生した。
貧しい人々に基本的なお金のやりくりの為のサービスを提供する世界で最初のマイクロファイナンス機関
普通の貯蓄サービスと貸出サービスを貧困層へ提供している。
グループではなく、ミーティングもない。→スタッフが日々個別に借り手を訪問
好きな時に好きなだけ預金したり、引き出したりできる。
最大4年までの貸付とできるときにできるだけ返済できる。
日々の生活のお金のやりくりとして様々な利用者がいる。
第五回マイクロファイナンスフォーラム(2)講演:澤田康幸氏(東京大学経済学部教授) ― 2013年01月12日
昨年12月16日(日)にNPO法人 Living in Peace主催の第五回マイクロファイナンスフォーラムが開催されました。
日 時:2012年12月16日(日) 14:00〜17:30
場 所:日本財団ビル
主 催:NPO法人Living in Peace (→ 公式HP )
Ustream中継:有り アーカイブは こちら でご覧になれます
プログラム:
▼第一部(14:00~15:50)
1.Living in Peace(LIP)理事長、慎泰俊による挨拶(5分)
2.講演:Stuart Rutherford氏(Safesave創設者)(20分)
3.講演:澤田康幸氏(東京大学経済学部教授)(20分)
4.LIPプレゼン「貧困削減効果を巡る学説紹介」(15分)
5.議論「グループレンディングと貧困削減効果」(50分)
▼第二部(16:00~16:30)
1.マイクロビジネスアワード概要
2.受賞者のビジネスに関して
3.受賞者登壇 質疑応答
4.現地式典、受賞者のビジネストリップ報告
東京大学経済学部教授 澤田康幸氏講演
開発経済学は1950年からあったが、20世紀は地位が低かった。
貧しい理由を机上の空論だけでなく検証できなかったため。
しかし、2000年以降見直されるようになり、MITでも今年博士号を修得する18人中6人が開発経済学。
不完全情報の経済学アプローチにより経済学的にも説明がつくようになった。
1970年代に利子補助融資したが40%の不履行率だったのに無担保で90%返済されるのがおかしいとされた。
なぜ成功したか理論的な理屈づけや実証的、実験的検証がなされなかった。
マイクロファイナンスの返済率はなぜ高いのか?
グループレンディングによる連帯が大切と考えられていた。
毎週行われるミーティングやグループだと借りる側が変な人と組みたくないという事で逆選抜の防止効果、お互いに適正な目的に利用しているか見たり、他人の債務不履行は自分にも不利益になるためグループの中での協力も生まれる。
マイクロファイナンスの効果について計測するため、医薬品の検証で使われるRCTという手法を使ったフィールド実験を行った。
フィリピンでグリーンバンクというMFIを利用している14,000人を対象に実験を行ったもの。
グループレンディングしていた人たちを無作為に個人融資に切り替えたが、返済率に統計的に優位な効果は
見られなかった。
どうやら連帯責任だけで高い返済率が実現されているわけではなさそう。
仮説では、返済すると次回借りられる額が増える前向きのインセンティブが働いているのでは?という事だった。また、毎週ミーティングが開かれるため問題がある人を早期発見できたり、みんなの前で借りたり返したりする心理的効果があるのでは?
マイクロファイナンスの新しい試みとしてインデックス型保険というものがある。
これはマイクロファイナンスの主要顧客である農家の収穫が天候に左右されるため生まれた保険。
降雨量に応じて保険金が支払われる仕組みで干ばつへの対策となる。
平年の半分以下の降水量になると25%の保険金が支払われ、全く降らないと100%の保険金が支払われる。
保険は保険金を支払う前に調査を行ったりしてコストがかさむが、降雨量のような指標に連動して支払うようにすれば調査費用も不要になる。
また、被害認定型と違ってモラルハザードも発生しにくい。
他にはウルトラプアプログラムと呼ばれるマイクロクレジットも利用できない人向けのプログラムや、土地なし農民への融資を収穫期に合わせて返済できるようにするプログラムも。
海外に出稼ぎにいくのをサポートするマイグレーションローンではVISA発行をサポートもしている。
課題:
お金を借りて何をするかが重要
例えば、家を人に貸すビジネスをした人は大きな成功を手にしている。
「高金利はいけない。搾取している。」という声により、上限金利を設定する国も出てきた。
結果、コスト圧縮で毎週から毎月へミーティングの間隔が伸びたり支店閉鎖といった動きも出ている。
有害な面としては日本の連帯責任制度を例に自殺につながるのではという意見もある。
頼母子講も自殺や娘をうったりした過去がある。
第五回マイクロファイナンスフォーラム(3)貧困削減効果を巡る学説紹介 ― 2013年01月12日
昨年12月16日(日)にNPO法人 Living in Peace主催の第五回マイクロファイナンスフォーラムが開催されました。
日 時:2012年12月16日(日) 14:00〜17:30
場 所:日本財団ビル
主 催:NPO法人Living in Peace (→ 公式HP )
Ustream中継:有り アーカイブは こちら でご覧になれます
プログラム:
▼第一部(14:00~15:50)
1.Living in Peace(LIP)理事長、慎泰俊による挨拶(5分)
2.講演:Stuart Rutherford氏(Safesave創設者)(20分)
3.講演:澤田康幸氏(東京大学経済学部教授)(20分)
4.LIPプレゼン「貧困削減効果を巡る学説紹介」(15分)
5.議論「グループレンディングと貧困削減効果」(50分)
▼第二部(16:00~16:30)
1.マイクロビジネスアワード概要
2.受賞者のビジネスに関して
3.受賞者登壇 質疑応答
4.現地式典、受賞者のビジネストリップ報告
LIPプレゼン「貧困削減効果を巡る学説紹介」
友人にマイクロファイナンスに関わっていると話すと「実際問題効果あるのか?」と聞かれて答えることができなかった。
そこで学者の意見を調べてみると論文でも意見が割れていた。
効果がある 17本
よくわからない 13本
98年に効果はあるという論文が出たが、異なる仮定で検証したらそんなことはないという論文も出た。
時には論文間で激しい論争も起きている。
マイクロファイナンスによる貧困脱出効果を計測するのが難しかったが、RCTという手法を経済に応用することで計測可能になった。
しかし、RCTは長期的な計測に向かないという問題もある。
サンプル数とコストが高いこと、そもそも他の金融機関が援助したら分類が崩れてしまうという問題も。
一方で「マイクロファイナンスの利用で将来を見つめるようになった。」という利用者の声がある。
無駄な支出を減らした
耐久消費財の消費が増えた
成功者だけではないが、金融のある世界は未来を描くことができるのではないか?
第五回マイクロファイナンスフォーラム(4)パネルディスカッション ― 2013年01月12日
昨年12月16日(日)にNPO法人 Living in Peace主催の第五回マイクロファイナンスフォーラムが開催されました。
日 時:2012年12月16日(日) 14:00〜17:30
場 所:日本財団ビル
主 催:NPO法人Living in Peace (→ 公式HP )
Ustream中継:有り アーカイブは こちら でご覧になれます
プログラム:
▼第一部(14:00~15:50)
1.Living in Peace(LIP)理事長、慎泰俊による挨拶(5分)
2.講演:Stuart Rutherford氏(Safesave創設者)(20分)
3.講演:澤田康幸氏(東京大学経済学部教授)(20分)
4.LIPプレゼン「貧困削減効果を巡る学説紹介」(15分)
5.議論「グループレンディングと貧困削減効果」(50分)
▼第二部(16:00~16:30)
1.マイクロビジネスアワード概要
2.受賞者のビジネスに関して
3.受賞者登壇 質疑応答
4.現地式典、受賞者のビジネストリップ報告
パネルディスカッション
Living in Peace理事長 慎泰俊氏
Safesave創設者 Stuart Rutherford氏
東京大学経済学部教授 澤田康幸氏
アジア開発銀行 福井龍氏
サミック センムン氏
Q.グループレンディングと貧困削減効果について現場ではどう考えられているのか?
Rutherford:
マイクロファイナンスには貯めると借りるという点がある。
これまではビジネス目的であることが多かった。
実際はお金が安全な場所にあることが価値という世界もある。
コツコツとそれを担保に大きな資金を借りることもあるため、それがないと困る。
貧困削減効果があるか?という質問が間違っている。
生活はよくなったか?という質問をすればそれについては良くなったという結果が出る。
澤田:
評価方法についてRCTは臨床治験から来ていて政策の評価などにも用いられている。
MITインドが104のスラムで検証したら平均的に効果はなかった。
ただし、もともとビジネスをやっていたり、やろうとしていた人がやると効果があった。
タイプによって効果に差が出る。
それが何なのか調べてみたところ、在庫管理のトレーニングすると劇的にコストが改善されることがわかった。
学者の役割は一般化して共有することにある。
Q.うまくいく場合とそうではない場合の違い
福井:
貧困から出るには特殊な現象が必要。
コミュニティー、文化、社会環境の強弱など。
政府金融も返済率が低いと言われるがミャンマーは短期間で成功した。
物理的には人口密度も関係する。
例えばアフリカとアジア。
人が集まってると成長効果が高いがアフリカはそもそも人が散らばっていてリーチするのだけでも大変。
また、信用情報が既に存在すると金融は成功しやすい。
MFI成功率インデックスというものは存在しない。
学者はこれだけみるので複合指標は向かない?
マイクロファイナンスについてはエピソードの固まりすぎという意見もあるが。
オポチュニティーを早くできないか?
ある人には効果があり、そうではない人もいる
Q.MFI成功率インデックスは作れないのか?
澤田:
信用力や国際間比較や信頼関係も複合インデックスはできるが、そこで把握できるのは全体。
個別性にはまっていくのが重要では。
Q.RCTのような人体実験的なものは全体には役立つが、経済開発の現場で他の方法はできないのか?
澤田:
アメリカでは倫理委員会を通してから実施している。
また、参加者にも事前にプログラムへの参加意志の確認はしている。
全部の地域が対象になるが一気には出来ない。そこで順番に実施することになるがそれはランダム。
くじは透明性がある。
自然実験という手法もある。
たまたまそうなっている条件を利用する。
例えば0.5エーカーの土地持ちで借りられる条件をつけると0.49エーカーの人と0.51エーカーの人は
さほど変わらない。そういう条件で違いを探す。
Q.マイクロファイナンスは効果がでるまでに時間がかかるのでRCTという検証手法は向かないのでは?
澤田:
その通りだと思う。
インドのスラムの研究でも短期の効果しかみていない。
長期でやろうとすると最初のオファーを待ってもらうことにもなる。
しかし、検証は他にも方法はある。
組み合わせて長期の効果もみている。
福井:
昔からそのように思っている。
調査は短期でも実際の現場では長期。
でも、そうするとノイズが入るので研究にならない。
仮説 オポチュニティーが増えたときどれだけ持続するか?そこに他の要因が入ってくる。
金融だけ見ていてもだめだろう。
アフリカはインフォーマルセクターは多い。
起業率 廃業率どっちも高い
平均ライフサイクルみるとサバイバルゲームの時にマイクロファイナンスで起業率をあげられるが
廃業率を下げられないかもしれない
うまくいっても少しかも。
Q.貸し手や借り手にとってのアプローチでよいものとわるいものとは?
福井:
マイクロファイナンスは正式に登録されているもので3500程度だが、それはほんの上澄み。
しかし中小規模は圧倒的にある。
そこでは利益率も悪くない。LIPはそこにアクセスしているし、そこに資金を出さないとよい成長は生まれない。
持続的でありながら社会的使命を果たす。
澤田:
ある村に過当競争がある。
インドで問題になり、徳政令がでたことも。
過当競争なのか適正な競争なのか検証が重要だが、研究はほとんどされていない。
産業組織論。
バングラデシュではNGOが母体が多いが、インドでは資金を外から集めるためコーポレート・ガバナンス構造という議論もある。
Q.なぜMFIがバングラデシュが多い中でそこで始めたのか?
Rutherford氏:
一つは必要とされていることに必要とされているサービスを提供すること
もう一つは自分がバングラデシュに住んでいたから。
1996年にマイクロファイナンスサービスが似通っていて違ったことを求めている人へ向けてサービスを開始した。
Q.なかなかファンドでお金が集まらないで困っていないか?また、LIPとの関係について
センムン氏:
LIPからサミックには5000万円出資していただいている。
パフォーマンス悪かったら返済額が少なくていいという仕組みなので結果的に他よりも金利が低く、ありがたい。
Q.マイクロファイナンスと商業銀行のちがい
小さい 豊かな都市部しか銀行がない
そういったことを変えるのがマイクロファイナンスと商業銀行とのちがい
金利も低くしたい
第五回マイクロファイナンスフォーラム(5)マイクロビジネスアワード授賞式 ― 2013年01月12日
昨年12月16日(日)にNPO法人 Living in Peace主催の第五回マイクロファイナンスフォーラムが開催されました。
日 時:2012年12月16日(日) 14:00〜17:30
場 所:日本財団ビル
主 催:NPO法人Living in Peace (→ 公式HP )
Ustream中継:有り アーカイブは こちら でご覧になれます
プログラム:
▼第一部(14:00~15:50)
1.Living in Peace(LIP)理事長、慎泰俊による挨拶(5分)
2.講演:Stuart Rutherford氏(Safesave創設者)(20分)
3.講演:澤田康幸氏(東京大学経済学部教授)(20分)
4.LIPプレゼン「貧困削減効果を巡る学説紹介」(15分)
5.議論「グループレンディングと貧困削減効果」(50分)
▼第二部(16:00~16:30)
1.マイクロビジネスアワード概要
2.受賞者のビジネスに関して
3.受賞者登壇 質疑応答
4.現地式典、受賞者のビジネストリップ報告
第二部 マイクロビジネスアワード
マイクロビジネスアワードとはLIPが企画、ミュージックセキュリティーズが募集しているマイクロファイナンスファンドで出資しているマイクロファイナンス機関で実際にローンを利用している人の素晴らしいビジネスを表彰しようという試みです。
プノンペンにあるサミックの新オフィスで表彰式が行われました。
サミック、セイラにティというカンボジアのマイクロファイナンス機関から20名を推薦していただき、日本の投資家が最終投票し、決定しました。
今回、アワードで二位になったオウク・サレンさんが来日されていました。
マイクロファイナンスファンド一口につき500円の協賛金がありましたが、サレンさんは賞金で発電機を購入することができたそうです。
サレンさんは今までに5本のローンを完済しており、完済の度により多くの金額を借りてビジネスを大きくしてきました。
最初は農業器具の修理から始まり、借りた資金を使ってパーツを購入して改良する仕事もするように。
今では地域の人に技術指導も行なっています。
若者がその技術を生かして仕事をするのを見るのが嬉しい、地域に貢献できるのは幸せと話していました。
サレンさんには来日中のビジネストリップの写真パネルが記念品として贈られました。
最後にサミックのセンムンさんのスピーチです。
マイクロビジネスアワードという取り組みはカンボジアでは初めての試みでした。
サミックからは10名をノミネートしましたが、彼らも日本に来たいと思っていました。
サレンさんの地元ではみんなが彼が日本に行くことを知っています。
彼は以前ロシアやベトナムで多くのことを学びましたが、今回日本でも多くのことを学ぶことができました。私はサミックのスタッフとしてこのアワードを毎年のように開催して欲しいです。
私にとって二度目の日本訪問でしたが、今回の旅では役に立ちそうなことを学びました。
新しい農業やハム、日本酒など。改めて美味しいと思いました。
もう一つは野菜を土を使わずに育てられるということです。いちご農家の技術もすごかった。
時間があったら自分でも試してみたいと思います。
日本に来て、人が勤勉でしっかりしていると思いました。
カンボジアに帰ったら日本のようになりたかったらしっかり勤勉に働くことが重要だと伝えたいです。
サミックへの出資についてとても役に立っています。
貧しい人々のニーズは食べ物と教育。
新聞などの記事でも政府はマイクロファイナンスに積極的です。
なぜなら彼らは効果に対して非常に積極的でポジティブだからです。
一つ、確実に言えることはお金がなければそこに向上、改善もありません。
小さい金額はすべてのキッカケになります。
サミックへの投資をお願いします。
それにより、より多くの顧客に融資を提供出来るようになります。
サミックへ投資するカンボジア4は今月末までの募集です。
詳しくは こちら
【関連記事】
第五回マイクロファイナンスフォーラムレポート
(4) パネルディスカッション
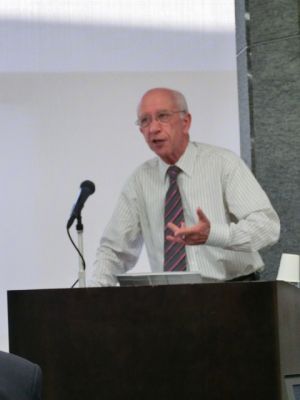






最近のコメント